就労継続支援B型事業所を利用するには診断書が必要?わかりやすく解説します
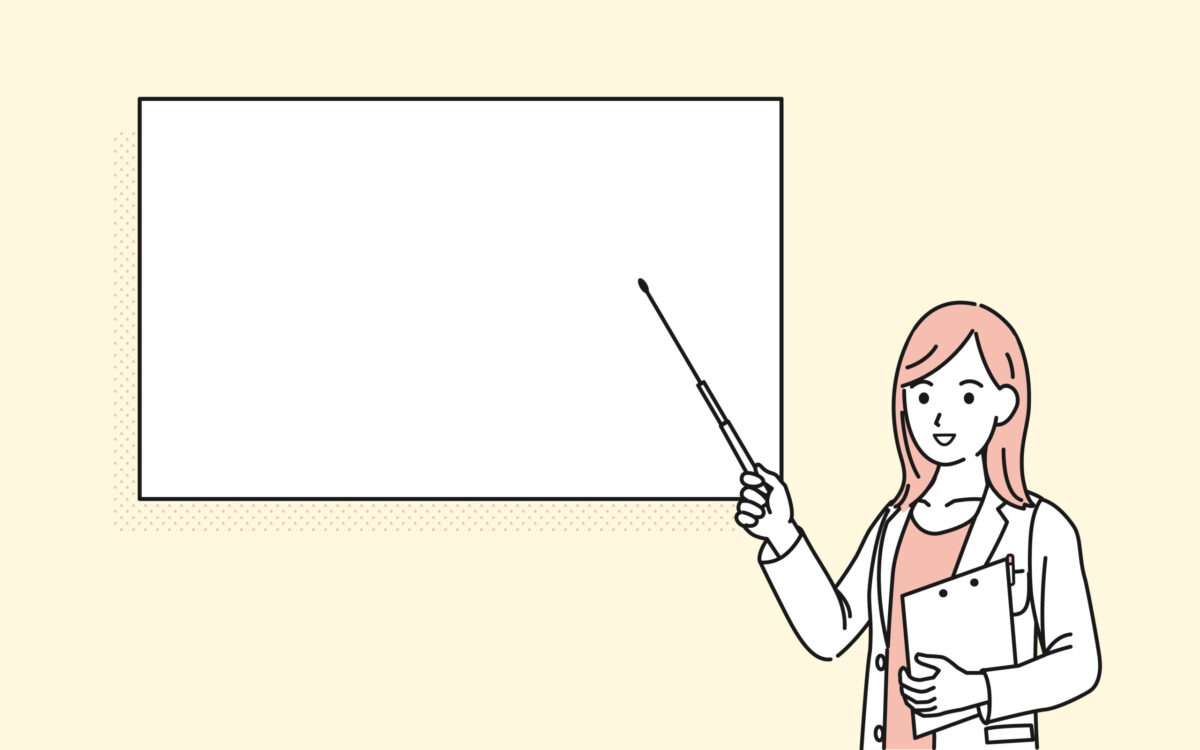
就労継続支援B型事業所は、障害や体調の理由で一般企業で働くことが難しい方が、自分のペースで働きながら社会参加を続けられる福祉サービスです。利用を考えるとき、多くの方が気になるのが「診断書は必要なのか」という点です。本記事では、診断書に関するポイントを含め、B型事業所の基本情報から利用までの流れまでをやさしく解説します。
就労継続支援B型事業所とは?
就労継続支援B型事業所は、障害福祉サービスのひとつです。年齢や障害の有無にかかわらず、体力やスキルに合わせて無理なく働ける環境を提供しています。特徴は「雇用契約を結ばずに通える」ことです。
主な対象者
- 精神障害や知的障害、身体障害がある方
- 医師の診断や自治体の判断により、一般就労が困難と認められた方
- A型や一般企業での勤務は難しいが、働く意欲がある方
利用のためには、市区町村に申請を行い「障害福祉サービス受給者証」を取得する必要があります。
利用時に診断書は必要?
結論からいうと、多くの場合「就労継続支援B型事業所」を利用するには診断書が必要です。これは障害の状態や就労が難しい理由を客観的に示すためです。
診断書が必要となるケース
- 障害者手帳を持っていない場合
- 医師の意見が必要と自治体から求められた場合
- 精神障害や発達障害など、症状の把握に専門的な判断が重要な場合
障害者手帳がある場合
すでに障害者手帳を持っている方は、診断書が不要なケースもあります。ただし自治体の運用によっては追加で診断書の提出を求められることもあります。まずは自治体の障害福祉課に確認することが大切です。
B型事業所で提供されるサービス内容
B型事業所では、作業を通じて生活リズムを整えたり、将来的にA型や一般就労へステップアップするための訓練が行われています。
主な仕事内容の例
- 軽作業(内職、シール貼り、封入作業など)
- パソコンを使ったデータ入力やデザイン作業
- 農作業や清掃、リサイクル関連の作業
- 手工芸品の製作や販売
訓練や支援の内容
- 生活習慣の安定
- コミュニケーションスキルの向上
- パソコンや事務作業のスキル習得
- 就職に向けた準備(面接練習や履歴書作成支援)
工賃(給与)はどのくらい?
B型事業所では「工賃」という形で収入を得られます。これは雇用契約に基づく給与とは異なり、作業の成果や事業所の収益に応じて支払われます。
- 全国平均:月1万5千円前後
- 高い事業所では3万円以上の場合もあり
- 作業量やスキルによって増えることもある
工賃は生活費をまかなうほどではありませんが、働いた対価を得る経験が自信やモチベーションにつながります。
利用開始までの流れ
就労継続支援B型を利用するには、いくつかの手順があります。診断書が必要な場面もこの流れに含まれます。
- 情報収集・見学
行きたい事業所を探し、見学や体験利用を行います。 - 市区町村に申請
障害福祉サービス受給者証の申請を行います。 - 診断書の提出
手帳がない方や自治体に求められた場合は、医師の診断書を提出します。 - 支給決定・契約
受給者証が交付され、事業所と契約を結びます。 - 利用開始
自分の体調やペースに合わせて通所が始まります。
就労継続支援A型との違い
B型とよく比較されるのが「就労継続支援A型」です。違いを整理すると次のようになります。
| 項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり(最低賃金が保証される) | なし |
| 給与 | 給与として支払われる | 工賃として支払われる |
| 対象者 | 一定の勤務が可能な方 | 一般就労やA型が難しい方 |
| 働き方 | 週20時間以上など勤務時間が定められる | 体調に合わせて柔軟に通所可能 |
このように、B型はより自由度が高く、体調や生活リズムに合わせやすいのが特徴です。
まとめ
就労継続支援B型事業所は、障害や体調の理由で一般就労が難しい方が、安心して社会参加できる場です。利用する際には「診断書が必要かどうか」が大切なポイントであり、障害者手帳の有無や自治体の判断によって異なります。まずは利用したい事業所や市区町村の窓口に相談し、自分に合った方法を確認することが大切です。
自分に合った働き方を見つける第一歩として、気になるB型事業所に見学や体験を申し込んでみましょう。医師や支援員と連携しながら、診断書の有無を含めた手続きを確認すれば、安心して利用を始められます。
就労継続支援B型は、働く意欲を持ち続けたい方にとって大きな支えとなります。まずは一歩踏み出してみませんか。

